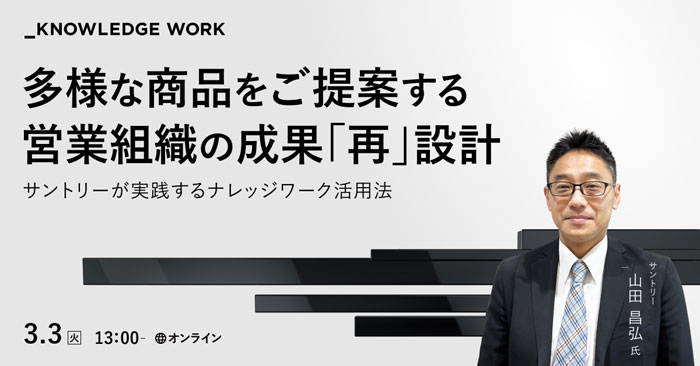東京海洋大学サラダサイエンス寄付講座は8日、「第5回サラダシンポジウム」を同大学品川キャンパスで開催し、対面とオンラインで110人が参加した。同講座は2013年10月からケンコーマヨネーズからの寄付により運営されており、大学院博士前期(修士)が対象。サラダや野菜の栄養や健康に役立つ機能に加え、品質、安全性、嗜好性、調理加工適性などに関する技術研究を行っている。研究室は3月で運営を終了し、シンポジウムも最終回となった。
シンポジウムでは、栄養面での野菜摂取の必要性や、機能性、品質、物性などに関する研究成果を発表。李潤珠特任助教による「サラダサイエンスにおける野菜の研究」では、サラダ素材として用いられるパプリカ、ピーマン、にんじんなどの野菜をブランチング処理せず冷凍・解凍し、テクスチャーや組織の変化を調べた。試験ではほとんどの野菜で冷凍・解凍により細胞構造が大きく変形しテクスチャーの低下が見られたが、パプリカは生でも冷凍・解凍後は細胞壁などの歪みが小さく、生鮮試料と比較してもテクスチャーが維持されていた。
枝豆を用いたブランチングの有無による凍結解凍後の香りについて調べた試験では、枝豆摂取前の香りはブランチング無試料がブランチング試料と比べ有意に良好であることなどが分かった。これらの試験結果からブランチングの有無による香気品質に影響を与えるのは莢(さや)であることが示唆された。

鈴木徹特任教授は研究室の活動を総括。研究室では立ち上げ当初から行ってきた食品の機能性研究に加え、鈴木氏の長年のテーマであった冷凍知見を取り入れた食感に関する研究までを手掛けてきた。鈴木氏は凍結濃縮したショウガの残さの成分に関する研究や、GABAに関する数々の研究、ブロッコリーの残さの新規用途開発などの事例を振り返った。
最後に壇上に立ったケンコーマヨネーズの島本国一社長は「サラダに用いる野菜や魚介・海藻類は鮮度保持が難しく、食材や調味料との組み合わせにより品質が大きく変化する。海洋大の水産で培われた冷蔵技術が重要な要素になるという理由からニチモウの協力を得て寄付講座を開設することになった」と経緯を述べた。島本氏は結びの言葉として「本講座を通じて、サラダ料理とサラダサイエンスはともに発展しないといけないことが分かった。皆さまには引き続きご協力をお願いしたい」と呼びかけた。