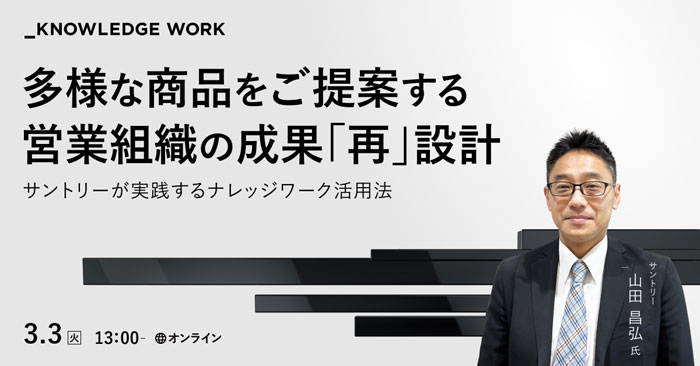飲料メーカー6団体で構成する公益社団法人食品容器環境美化協会(食環協、那須俊一会長)は飲料容器(缶、ビン、ペットボトル)を中心に食品容器の散乱防止を図り環境美化に努めることを目的として、1973年に任意団体からスタートした。活動の一つとして、アダプト・プログラムの普及推進がある。一般には聞き慣れない言葉だが、アダプト(Adopt)とは英語で「養子縁組」を意味し、アダプト・プログラムとは、一定区間の道路や公園、駅前通りなどの公共スペースを養子に見立て、地元市民や企業団体がわが子のように愛情をもって面倒をみて(清掃美化など)、自治体がそれを支援する市民協働の仕組みである。1985年アメリカが発祥とされ、日本で最初に導入されたのは1998年、今日では全国500を超える自治体が導入し、700以上のプログラムが稼働。そこで食環協の山本景一専務理事に、アダプト・プログラムの現況や課題などについて聞いた。
――アダプト・プログラムにおける食環協の役割について教えてください。
山本 アダプト・プログラムは市民と行政、主に自治体が協働で進める新しい「まち美化プログラム」で、食環協が「認定」「登録」するといったものではなく、導入のイニシアチブは自治体にあります。主役である市民、自治体をサポートするのが食環協の役割で、現在では①情報センターとしての機能の発揮②活動団体に対する助成③地域における普及促進――の三つの事業を実施しています。
一つ目の情報センターとしての役割では、協会のホームページの掲出を中心に、制度紹介にとどまらず、アダプト制度の運用の参考になるよう、アダプト・プログラム実施上の課題・悩みへの対応方法や解決のヒント、ユニークな取り組み、成功事例など幅広い情報の提供に取り組んでいます。複数の自治体担当者を集めた意見交換の場を兼ねたセミナーの開催のほか、情報収集にあたっては、導入自治体を対象にしたアンケート調査、訪問取材など、また、情報発信にあたっては、ホームページやFacebookを活用したアダプト・プログラムの紹介、パンフレットやDVDの提供などを行っています。
二つ目の活動団体に対する助成は、アダプト活動を始めようとする市民団体、活動をさらに充実・拡大しようとする市民団体を対象に、清掃活動やポイ捨て防止活動に必要な経費について助成を行っています。助成した団体はホームページなどで紹介しており、団体自体の活性化に加え、広くアダプト・プログラム活動の紹介に貢献しています。毎年多くの応募を頂戴していますが、募集は自治体を通じて行っており、このことにより自治体の団体に対する求心力を高める側面もあると思っています。
三つ目の役割は、地域におけるアダプト・プログラムの普及です。特色ある活動事例の紹介のほか、連携している団体への支援、環境イベントへの参画・出展、アダプト・プログラム教室への講師派遣などを実施しています。
――活動団体に重要なことは何ですか。
山本 アダプト・プログラムにとって重要なことは、活動を長く続けられるように留意することだと思います。例えば、一斉清掃とは異なり、基本的には少人数でも長く活動を続けることを目指しています。当協会主催のセミナーに講師を依頼している先生は、「1000人が1回清掃するのではなく、10人が100回清掃する方が大事です。少人数でも100回続けるほうに意義があり、連続して参加した人たちの方が美化意識が高まり、地元に対する愛着心も湧くでしょう」とおっしゃっていました。これがアダプト・プログラムにおいて重要なことで、モチベーションを維持するため、活動団体名を表示したサインボード(看板)の掲示や活動を自治体広報誌に紹介、さらに表彰するといったことを多くの自治体が実施しています。
また、アダプト・プログラムを行うにあたっては、あまり肩に力が入っていては長続きしません。あくまでもボランティア活動なので、参加者には、いわばリピーターになってもらって、続けてもらうことが大事です。半分観光的なイメージで、子どもたちにも参加してもらえるような、遊び感覚も排除せず楽しみながら行ったほうが長続きして、人も集まってくれると思います。
――アダプト・プログラムの認知を広げるにはどうしたらよいでしょうか。
山本 導入している多くの自治体で、活動団体の減少、参加者の高齢化といった課題に直面しています。若い人を中心にして、活動を広く知っていただくことは大切です。決め手はありませんので、基本は、市民の皆さまに呼びかけるということしかなく、ホームぺージや広報誌に加えて、自治体によっては、SNS、アダプト・プログラム独自の広報誌、イベント参加出展のほか、自治会や関係企業を直接訪問して説明するといった地道な努力をされ、効果があったというアンケートの回答もあります。
概して、自治会・町内会という地縁的団体はアダプト・プログラムの参加団体としては減少傾向で、ESGやSDGsの流れの中で、地元企業の参加が増えている印象です。