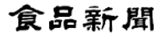アルミ缶入り日本酒のパイオニアとして知られる新潟の菊水酒造。1972年発売の元祖生原酒缶「菊水 ふなぐち」は累計出荷本数が3億本を超える。そんな同社が今夏にボトル缶の新充てん機を導入するなど、新たな挑戦に乗り出している。本紙の取材に髙澤大介社長は「デイリーの日本酒はアルミ缶でカジュアルに楽しんで欲しい。容器と容量の2軸で飲酒シーンを提案し、お客様の変化に応えていく」と語った。
■小容量で手軽&おいしさキープ

日本酒の容器は一升瓶(1・8L)や四合瓶(720ml)が主流だが、近年はアルミ缶(180ml・200ml・500mlなど)の存在感が徐々に高まっている。小容量で手に取りやすいこと、遮光性が高くおいしさをキープできることなどが評価され、大手・中小問わず多くの酒蔵が商品化するようになってきた。
菊水酒造が「菊水 ふなぐち」を発売した72年、日本酒の消費量は最盛期にあり、一升瓶が大半だったという。その一方、当時の世間は高度経済成長を背景に旅行やレジャーを楽しむことが一般化。髙澤社長は「いずれ小容量でハンディな酒が必要になってくると先代社長(故髙澤英介氏)は考えていた」と述懐する。
そして酒蔵来訪者だけに振る舞っていたしぼりたての生原酒が大変好評だったことも開発を後押しした。製造工程を全面的に見直し技術的な課題をクリアした上で、品質劣化を防ぐアルミ缶入りの日本酒に行き着いた。
市場でヒットするまでには数年を要したが、現在、同社のアルミ缶入り清酒の供給能力は日産で最大10万本におよぶ。いまや「菊水 ふなぐち」はレギュラー品(200ml缶)を中心に、熟成タイプ、季節酒、スパークリングとラインアップも充実。“コンビニ最強酒”の異名を持つまでに定着し、50年以上にわたり培ってきた生酒や缶入り清酒に対する知見が国内トップクラスであることも疑いようがない。
その強みを活かし、実は複数の酒蔵よりアルミ缶製品への充てん作業を受託。昨年ごろから問い合わせが増え、今年2月から本格的に対応しているという。委託元はボトリングラインに設備投資しなくても商品化でき、市場のニーズに応えられるメリットがある。現状は4蔵から請け負っているが、近い将来にも10蔵程度まで増える見通し。
他の酒蔵とも連携を図り、業界の中でアルミ缶製品のプレゼンスを高めていきたい考えだ。
■新たな価値提供で市場創造

背景には、髙澤社長の「デイリーの日本酒をもっとカジュアルに楽しんで欲しい」との想いがある。加えて、今後さらなる生活スタイルの変化や飲酒量の減少を予測。「日本酒にとって消費環境はますます厳しくなる」との認識を示しつつ、「500mlサイズでリキャップできるボトル缶はこれからの飲酒スタイルに合致する」と期待を寄せる。
かつて「菊水 ふなぐち」で小容量のアルミ缶清酒をヒットさせた先駆者だけに「新たな価値を提供して市場を創っていきたい」との意気込みだ。
新ラインでは容量の変更が可能。500ml缶に限らず、商品設計にあわせて300ml缶など多様な容量のボトル缶に詰められる。

髙澤社長は「お客様の飲酒量は減少傾向にある」ことを指摘。その上で「従来通りたくさん飲まれる方もいらっしゃるが、これから先は1日1杯だけ嗜むなどの方も増えてくる。容量の大きい瓶製品(1・8L、720mlなど)は業務用や贈答用に適しているものの、家庭用は小容量のニーズが一段と高まるのではないか。日常酒の世界で200mlのアルミ缶やリキャップできる500mlのボトル缶は選択肢の1つになり得る」とアピールする。
一方、SDGsの観点からもアルミ缶は優位性があると強調。アルミニウムの原料であるボーキサイトを精錬しなくても、「CAN to CAN」で再資源化できることや、瓶に比べて軽量かつ省スペースなので、家庭や店頭での保管、さらに物流面でも利点がある。髙澤社長は「デイリーに楽しむ日本酒の容器が環境に優しいことも大切になってくる」と展望する。