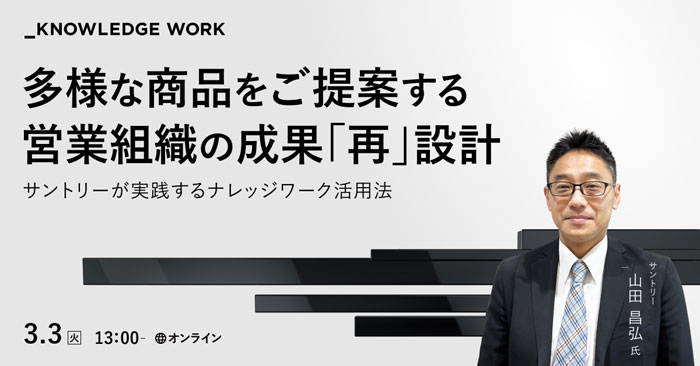有明海の大不作で前年から2割以上も生産枚数が減少した2022年度の国産海苔。韓国産への切り替えが加速するなか、海苔商社からは養殖と加工流通との仕切りを見直すべきとする声が多くなっている。
22年度漁期、海苔の共販枚数は最盛期の半数に満たない48.4億枚だった。背景にあるのは、21年度漁期で国内生産の6割を担っていた有明海の大凶作。佐賀有明・福岡有明がいずれも半作で、熊本有明も2億枚近くの減産に終わった。
漁期中は、40億枚割れも囁かれるなど深刻な原料不足への懸念から買いが強まり、一時は前年の2.5倍にまで入札単価が暴騰した。量のみならず質も悪く、上モノが手に入らず休売となる商品もあり、海苔業界全体に大きな打撃を与えた。
大手海苔メーカー各社は、6月から一斉に値上げを実施。流通での売価反映を8月までにおおむね完了しており、これから消費者の反応が見えてくる。
11月から始まる23年度漁期では有明海の生産回復に期待が集まるが、「不作の要因は一過性ではない」とする厳しい見方もある。雨不足による栄養塩の減少や赤潮の発生に加え、海水温の上昇をもたらす温暖化や生産者数の減少など、解決が難しい問題も含まれるからだ。
海苔商社などは、生産者の負担軽減と生産量の拡大を同時に実現できる方法として、一次加工法人の設立による海陸分業の推進を考えている。養殖=海の仕事は漁業権のある漁業者しかできないことから、陸の仕事=乾海苔を作る一次加工を分担できないか、という発想だ。
日本の海苔漁師は、海での養殖に加えて自ら購入した機械による一次加工も行っており、長期間にわたる購入代金の返済が新規参入や後継者探しを難しくする一因になっている。法人運営の加工所に原草を持ち込む形が一般的になれば、ローンの負担がなくなり海の仕事に専念することができる。
海陸分業のモデルとされる韓国は、愛知県の年間生産枚数に相当する2億枚を加工できる工場がいくつも建てられ、年間百数十億枚を生産する世界最大の海苔生産国となった。日本でも同様のイノベーションを起こせないか。業界の動きに期待したい。