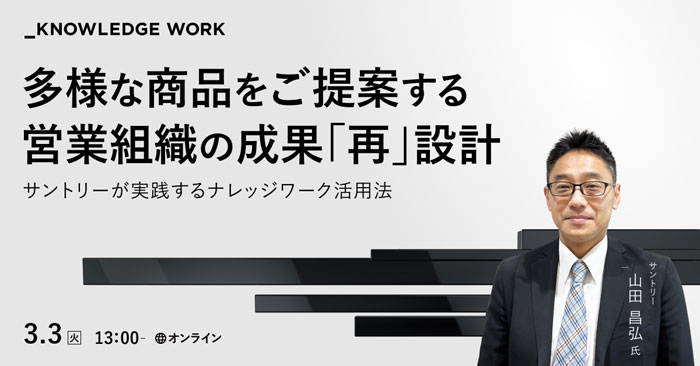関西に根付いた水炊き文化を盛り上げようと、Mizkan大阪支店は10月29日に外食店オーナーやマスコミを招いて発表会を催した。
「水炊き」は昆布やかつおでだしをとり、素材の味を引き出して食べる、関西を代表する鍋料理。最初から味付けをする関東の「すき鍋」とは一線を画す。江戸時代に北前船によって大阪に北海道産昆布がもたらされ、また関西の軟水と相性が良かったこともあり、昆布を使う水炊き文化が継承された。
いまでこそ水炊きにはぽん酢が合わせられるが、ぽん酢はもともと江戸時代にオランダから柑橘系カクテルとして入ってきたもので、明治時代に鍋料理の普及とともに調味料として広がった。
Mizkanの第7代目中埜又左衛門が博多で、鶏の水炊きの漬けだれとして出された味付けぽん酢に出会い、これをヒントに商品を開発。1964年に「ミツカンぽん酢〈味つけ〉」を発売して、これまで外食店で食べられていた水炊きが一般家庭で普及。その後同社が、焼き魚やハンバーグなどの調味料としてメニュー提案を強化した結果、通年商材のぽん酢が定着した。

発表会では、かつての柑橘と醤油を合わせたぽん酢と、Mizkan「味ぽん」の味くらべ。また進化系水炊きとして御所坊やさかばやし(神戸酒心館)、日本料理・湯木の創作鍋の試食を提供した。これらの鍋は各店舗で一般提供する。
冒頭に稗田旭大阪支店長があいさつを行い、「昨年に『味ぽん』が発売60周年を迎えた。今回の企画を通して、地元の名店には地域食材を使った、ユニークな水炊きを創作してもらった。素材の味を生かした水炊きと、ぽん酢との相性を見直してもらうきっかけになって欲しい」などと話した。