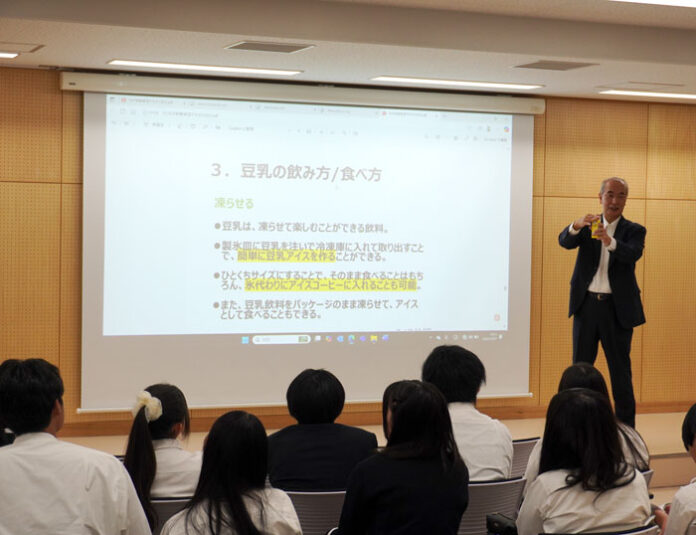日本豆乳協会は7日、東京都立赤羽北桜高等学校の1年生調理科の男女36名の生徒を対象に「豆乳食育移動教室」が開催した。2013年より開始した移動教室は、日頃から栄養や食物、調理に関心の高い生徒を対象に豆乳啓発活動の一環として実施。過去10年間には65校で行われ、累計1,500名が受講。赤羽北桜高等学校では昨年に引き続き2回目の開催になった。
移動教室では安部徹事務局長から協会概要や豆乳の歴史、生産量、スライドによる製造工程、栄養成分、SDGsについて説明した。
主に植物性たんぱく質としての豆乳視点で進められ、この中で安倍氏は、
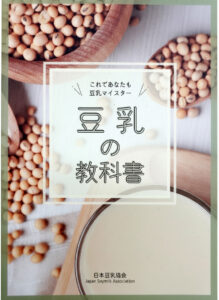
「たんぱく質を構成するアミノ酸には20種類があり、このうち9種類は体内では作れないため、豆乳を飲んで補ってほしい。動物性たんぱく質は牛乳や牛肉・豚肉類、植物性たんぱく質は大豆や豆乳に含まれるが、なぜ豆乳がたんぱく質を手軽に摂れるかというと、豚バラ肉100g中には14・4gしかたんぱく質が含まれていないが、大豆100g中には33・8gも含まれているため、効率よく摂取できる。豆乳にはイソブラボンやサポニン、レシチンなど様々な機能を持つ栄養成分が豊富に含まれている」ことなど説明。「動物性、植物性には互いにメリットがあるが、大豆たんぱく質の豆乳は、アミノ酸がバランスよく摂れる」とし、今年制作した「豆乳の教科書」を参考にしながら、豆乳の栄養効果について詳しく説明。授業の最後には調整豆乳と無調製豆乳の飲み比べや豆乳を使った料理やお菓子作りなども紹介した。