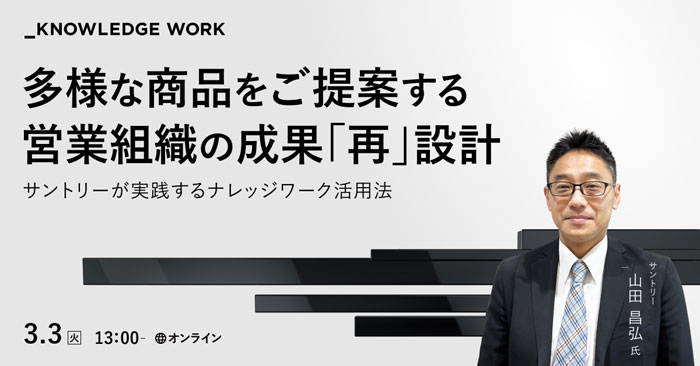大塚食品のビタミン炭酸飲料「マッチ」は1996年の発売開始から約30年間、高校生に寄り添い、毎年、新しい高校生ユーザーを獲得するとともに、昔飲んでいた大人がCMなどをきっかけに再び飲み始めるという好循環が生まれ2021年から連続成長を遂げている。
6月13日、取材に応じた堀内雄大製品部飲料チームマッチ担当PMは「高校生のときに『マッチ』を飲まれた方が、大人になった時に思い出して買っていただく動きが近年鮮明になってきていると感じる。発売当時10代だった方が40代の親世代になり、家庭内で親から子へ『マッチ』を伝えていただく“循環”も今後期待できる」と語る。

販売数量の対前年比は22年が17%増、23年が7%増、24年が8%増。いずれの年も炭酸飲料市場の伸びを大幅に上回る数量成長を遂げ、今年1-5月も3%増と好調を維持。今年1-5月炭酸飲料市場は、インテージSRI+によると数量ベースで6%減と推定される。
健康志向の高まりで糖の摂取を避ける“避糖化”の動きがある中で、大人が再び飲み始める要因は、高校時代の飲用体験に加えて、独自フレーバーと微炭酸を掛け合わせたおいしさと飲みやすさ、1日分のビタミン入りの健康感にある。
独自フレーバーについては「ユーザーの方にとって『マッチ』は、唯一無二の『マッチ』味として認識していただいている」とみている。
飲みやすさは、微炭酸設計で実現。一般的な炭酸飲料は、ガス圧により一度に多く飲めないのに対して、「マッチ」は軽い運動をして汗をかいた時においしく飲める炭酸飲料として微炭酸設計で開発された。

今年、開発時の原点回帰を図り、軽い運動など“何かした後”の飲用シーンの訴求に特化したマーケティング活動を展開している。
同社がデータを分析したところ「マッチ」は他の炭酸飲料と比べてスポーツの後や勉強を終えた後に突出して飲まれていることが判明した。
「単純に炭酸飲料として飲まれてしまうと『マッチ』の魅力が伝わらないことから、今年は“何かした後”の飲用シーンにこだわって展開している。そこから派生して風呂上りなどのシーンへと広がると考えている。“このシーンでは『マッチ』だよね”という世界観をつくっていきたい」と述べる。
この考えのもと、4月11日に、次世代シンガー・乃紫(のあ)さんが書き下ろした楽曲の新WEBCMを公開し、放課後や部活の後など“その後に訪れる”高校生の“もう1つの青春”を伝えたところ、新規ユーザーと昔飲んでいた大人の両方を獲得するという好循環が加速している。春先に配荷が拡大したことも手伝って5月単月の販売実績は17%増となった。
「10代の購入率が上がり、それに加えて20、30代の上の世代の購入率も上がった。高校生をターゲットにしたコミュニケーションだが、上の世代からも共感いただいたのかもしれない」との手応えを得る。
共感を得る施策に加えて、高校生との接点拡大施策として高校生サンプリングを今年も実施。全国50万人への配布を予定し既に9割程度配り終えたという。
「同じ高校に毎年配布したとしても、入学・卒業は毎年行われているため、必ず新規の高校生にアプローチできる」との考えのもと毎年実施している。

幅広い層のトライアル獲得には、派生品の「ビタミンみかん」に期待を寄せる。1-5月の販売数量は1桁上昇した。
その役割について「『マッチ』を初めて見られた方からは“どんな味かわからない”というお声をいただくのに対し、『ビタミンみかん』はみかんやオレンジの味が想起されやすくトライアルにつながりやすい」と説明する。
「マッチゼリー」は、小腹満たしとリフレッシュの2つのニーズに対応できるものとして提案し配荷拡大を図っていく。
「学習塾などで、お菓子や一般的なゼリー飲料で小腹満たしをする際、恥ずかしいと思われる方もいるという。その点、『マッチゼリー』はペットボトル形状であるため水分補給をするかのように小腹満たしができ、さらに微炭酸となっているため、冷やして飲めばリフレッシュもできる」と胸を張る。
なお、全国清涼飲料連合会の「2024年清涼飲料水生産数量及び生産者販売金額」によると炭酸飲料の生産者販売金額は2020年が前年比4.9%減の7147億8000万円、21年が4.9%増の7495億2400万円、22年が3.1%増の7728億9600万円、23年が2.9%増の7953億円200万円、24年が10.5%増の8789億8000万円。
炭酸飲料の生産量は20年が5.3%減の374万9100KL、21年生産量は1.4%増の380万800KL、22年が横ばいの380万1200KL、23年が0.6%減の377万8600KL、24年が3.1%増の389万6300KL。