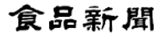1896年(明治29年)、翠田辰次郎氏が富山県総曲輪でラムネの製造販売を開始して創業したトンボ飲料。
トンボ飲料の経営理念の一丁目一番地には、五代目・翠田章男社長が掲げた「我々は、難度の高い仕事に取り組むことにより、人間として成長する」がある。
「私の人生観は職業観と同じ。会社として掲げているものは私の人生観。“難度の高い仕事に取り組む”としたのは、難度の高い仕事に取り組むことで人間として成長すると考えたため。人生の目的というのは人間として成長することだと思っていて、仕事を通じて自らの人格を高めていく。我々はそのような価値観を共有する集団となる」と力を込める。

社員は、このような考え方に根差し、TSV(トンボシェアードバリュー)の活動に取り組んでいる。
TSVとは、社会価値と経済価値の共創をテーマにするCSVを独自に解釈したもの。以下の3つの柱+SDGsとしている。
――社員の成長による共創
――環境に配慮することによる共創
――健康と福祉に役立つことによる共創
――SDGsへの取り組み
これらの中で独自色が強いのが、社員の成長による共創の一環として2012年から実施している社員の提案制度。
提案制度は、毎年1人1件のアイデア出しを課すもの。アイデアは、他部署や会社全体の改善につながるものを募集している。
社員から上がってきたアイデアは全社員に共有され、最初に社長が方針を決める。アイデアが採用されれば関係部署に回され、不採用の場合もその理由を説明するフォローのコメントが入る。
過去には提案制度により、子どもを持つ女性社員の時短勤務が先駆けて導入されたほか、雨傘入れが不特定多数のビニール傘で乱雑になるといった課題には、傘入れの各穴にネームを記すことで劇的に改善した。

3か月ごとにインセンティブを設け、よいアイデアを提案した社員には金一封を支給している。
社員にアイデア出しを求める背景には、社員の人間としての成長に加えて、創業期からのDNAによるものと思われる。
創業者の翠田辰次郎氏は「かなりのアイデアマンだった」という。
富山市八尾町は、蚕(カイコ)を育てる養蚕業が盛んな土地。創業者はもともとカイコが卵を産み付けさせた蚕種紙(たねがみ)を柳行李(やなぎごうり)に積み、全国を行商していた。
その道すがら、東京の深川あたりでラムネに初めて出会う。その味わいに衝撃受けた創業者はラムネ屋への転身を即決。ラムネ屋に作り方を教わり、1896年(明治29年)、富山市総曲輪で翠生舎(トンボ飲料の前身)を創業。ここでラムネの製造販売を開始しブランド名を「トンボ」と定めた。
ブランド名も機知に富んでいる。
「水面すれすれところを飛ぶ姿が涼しげで清涼感があるということでトンボと命名したと聞いている。トンボの漢字(蜻蛉)の虫偏(むしへん)を氵(さんずい)と冫(にすい)にすると清冷となることも加味したという」と説明する。
新型ラムネ瓶も考案する。
ラムネ瓶のビー玉をとどめておくくびれ部分がネックとなり回収後の洗浄が困難なことから、くびれを底部分に移動させる底玉式ラムネ瓶を編み出し「ミスタ式底玉ラムネ」として発売する。
底玉式ラムネ瓶はそれまでのラムネ瓶と比べ洗浄効率が劇的に向上し、瞬く間に全国のラムネメーカーに広まり、瓶容器は海外にも渡った。

ビー玉が底まで落ちるため泡が吹きやすいという欠点には、創業者が木目の荒い杉材製の「玉押し」を考案。木目を透かして炭酸を逃がすことで解決した。
ラムネに続くラインアップとして「ラボンサイダー」も考案。ラボンとは遠い南国をイメージした空想の産物で「レモンのような、ピーチのような、オレンジのような…不思議な味わい」(翠田辰次郎氏・談)に仕立てられ、富山県では一世を風靡した。
1945年(昭和20年)8月、米軍の富山大空襲により富山市全域が焼失。ラムネ工場も失われた。二代目・翠田邦志氏はその焼跡に立ち尽くすも、すぐさま「トンボラムネ」の再生を決意。直ちに工場を再建し、ラムネの製造を再開した。

高度成長時代のキャバレーのお土産だったシャンメリーをファミリーユースに育てて、米国ローヤルクラウンコーラ社と北陸エリアでのフランチャイズ契約を締結して「RCコーラ」を学校周辺マーケットに浸透させたのは三代目・翠田康志氏。
三代目とともに戦後のトンボ飲料の歴史を担ってきた四代目・翠田福三郎氏は、アイスクリームの過大投資後の資金需要の苦しいトンボ飲料の屋台骨を懸命に支えた。
五代目・翠田章男社長は先代の流れを引き継ぎ新事業に挑戦。受託生産事業を中身開発に踏み込んだODM(オリジナル・デザイン・マニュファクチュアリング)事業へと発展させる。